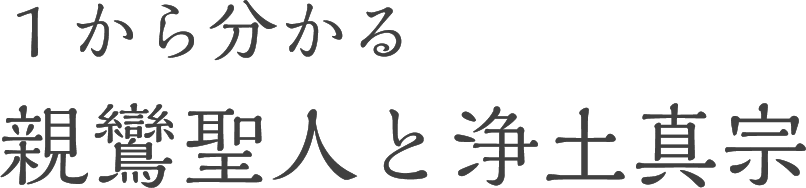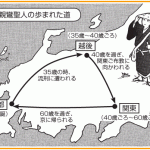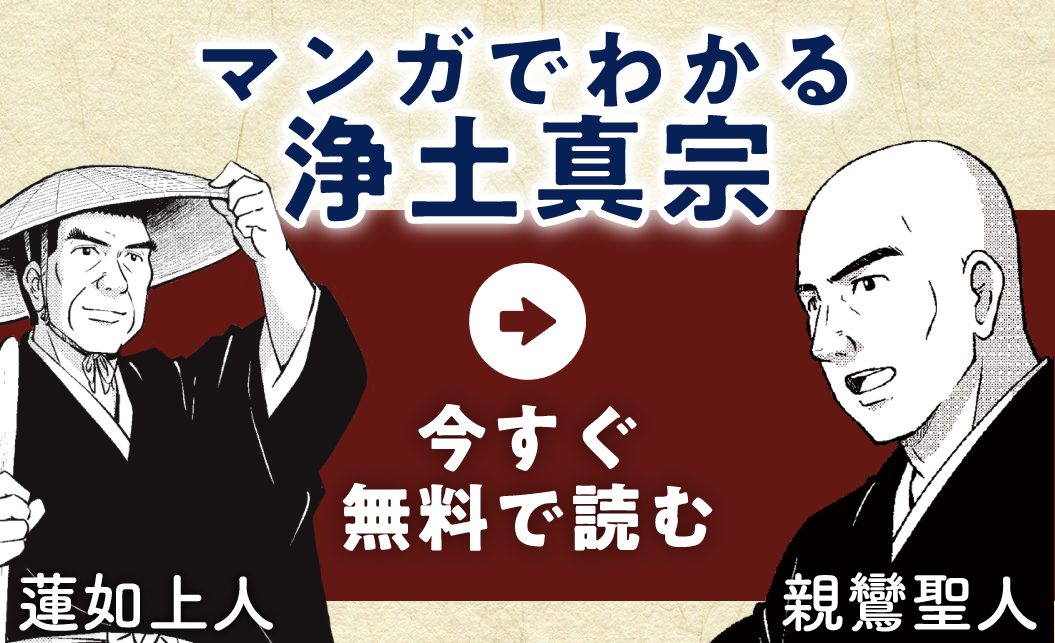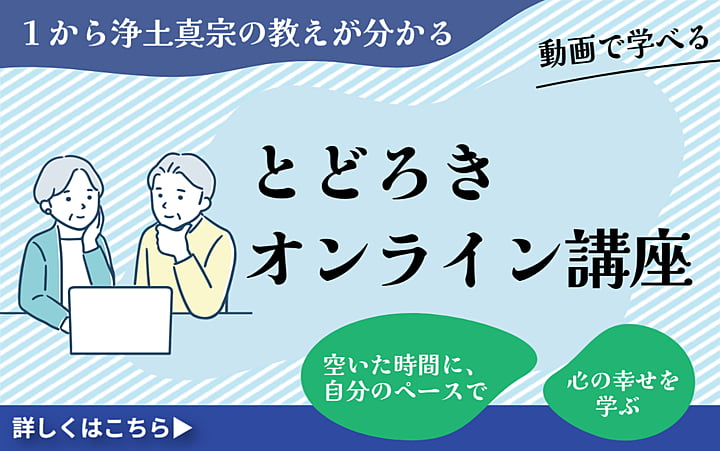AIの進化により幸せのカギである「人間とは何か」が問われる
今年は「人間とは何か」が問われる年になる
年頭に、「日経ビジネスオンライン」の編集長が、こんなタイトルの記事を公開、その背景の一つとして「AI(人工知能)」の進化を挙げています。
人工知能の学習能力が向上し、判断や思考などで、より人間らしい能力を発揮し始めました。
作曲や小説執筆などの芸術活動も可能になり、遠くない未来に、人間からさまざまな仕事を奪うのでは、といわれています。
そうなれば私たちの存在意義はどうなるのか。
「人間とは何か?」の答えが、いよいよ求められてきます。
世界の三大聖人のトップに挙げられるお釈迦さまが仏教に説かれたことは、「どんな人でも本当の幸せになる道」一つでした。
そのお釈迦さまは、仏教とは一言でいえば「法鏡」であると仰っています。
「法鏡」とは、本当の私の姿を映す鏡ということですが、それはどんなことでしょう。
自己を知ることが本当の幸福のカギ
スポーツも受験も就職も、自分の実力を知らねば勝利は期待できません。
かの有名な孫子(中国、春秋時代の兵法書。孫武の作とされる)の兵法に、
「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」
との名言がありますが、「自己を知る」は、何事においても重要な一歩です。
哲学発祥の地、ギリシャの神殿には、「汝自身を知れ」と刻まれています。
「私とは何ぞや?」の問いこそ、何千年も前から人類が知りたいと思ってきたことなのです。
「私」が幸せになるには、その「私自身」を知らねばなりませんから、人間の「幸福」を真正面から探求する哲学とは、「人間自身」の探求にほかなりません。
エジプトのスフィンクスが、
「始めは4本足、中頃は2本足、終わりに3本足となる動物は何か?」
と、砂漠の旅人に問いかけ、答えられない者を食い殺したという伝説があります。
ハイハイから二足歩行を覚え、晩年、杖に頼る一生を例えたこの謎かけは、自己を知らぬ私たちに警鐘を鳴らしたものでしょう。
お釈迦さまがお亡くなりになる時、
「我は汝らに、法鏡を授けるであろう」
と仰ったのは、「私自身を知る」ことが本当の幸せの扉を開くカギであり、それが仏教の教えであるという表明です。
「仏道を習うは自己を習うなり」
仏教を聞き、本当の自分の姿が知らされた時、私たちは「本当の幸せ」になれるのです。
仏教に説かれた本当の私とは?
「知るとのみ 思いながらに 何よりも 知られぬものは 己なりけり」
誰でも、自分のことは自分がいちばんよく知っていると思っています。
しかし「私」とは、近すぎてかえって見えないもの。
「目、目を見ることあたわず」
と言われるように、どんなに視力のいい人でも、自分の目で、自分の顔や目そのものを見ることはできません。
そこで必要になるのが鏡というものです。
お釈迦さまは、世に「私」を映す3とおりの鏡があると説かれています。
それはどんな鏡でしょうか。
(1)他人鏡 他人の評価によって知る自分の姿
私たちは、どんな時でも他人からどう見られているか、その「評価」が気になります。
他人の評価によって私の「幸福」が決まると思って生きる私たちは、「他人の鏡に映った自己がどんなものか」に、日々、神経をとがらせて生活しているとさえいえましょう。
「インスタ映え」と聞いて、何の「ハエ?」という人もあるかもしれません。
多くの人が見栄えのいい写真を撮って、すぐにスマホで友達に見せています。
本来、友達同士で楽しみを分け合うはずの行為が、写真写りばかりに気を取られ、逆に憂鬱になると悩む人は多いようです。
「いいね!」と言ってくれる人数が気になり、最近はそのボタンをたくさん押してくれるサービスをお金で買える、「いいね!自動販売機」なるものさえもある。
仕事をしていれば、“今日のネクタイ、昨日と同じじゃダメだよね”と朝からあれこれ思い悩む。
足下を見透かされないように靴を磨き、ツメが甘いと言われないよう、大事なお客さんに会う前には爪を切り、10分前には洗面所で歯を磨く。
もちろん、ブレスケアガム、デオドラントスプレーの携行は必須。
「人は見た目が9割」などとあおられると、昇進も外見一つで決まるとばかり、上司にも顧客にも「よく見られたい」と必死です。
昼休みも気は休まらない。同僚や後輩と「うな重」でも食べに行こうものなら、さらなるつらい選択が課せられます。
先に注文した2人が、威勢よく「松!」とくれば、自分だけ「梅」と言えず、出費を思って震える声で「オレも松!」と叫んだものの、味も分からず店を出る。
冠婚葬祭に包む金額に気を遣い、新年のお年玉もまた試練。
親戚の子がその場で開けて、「え、今どき3000円」などと言おうものなら、心でその子をたたきつけている。
年始早々、心穏やかではいられない。
教育現場では、親の目を気にして、先生や保育士がへとへとになる。
学芸会や運動会の時期ともなれば大変。
『花咲かじいさん』の劇で、せっかく出てきたわが子が「木」の役だったら親はどう思うか。
最近はすべての子が役からあぶれないよう、主役も意地悪じいさんも何人もで演じるそうな。
もちろん、他人の目を気にするのは大事なことですが、「私の幸福」まで「他人の評価」が決めるのでしょうか。
今日ほめて 明日悪くいう 人の口 泣くも笑うも ウソの世の中
と一休が嗤っているように、人は私を「都合」によって評価するのですから、他人の評価など、都合次第でコロリと変わります。
昨年3000円のお年玉で「ケチなおっちゃん」とレッテル貼られたおじさんも、今年1万円渡せば「いいおじちゃん」に早変わり。
みんな自分にとって都合のいい人が「いい人」なのです。
しかし、「ブタは褒められてもブタ ライオンはそしられてもライオン」、クルクル変わる他人の評価が、私の真価を表すはずがありません。
「悪口を言われても気にする必要がない。どうせ、もうすぐ皆死ぬのだから」
『徒然草』の吉田兼好が書いたそんな忠告で、とっても気が楽になったという人がたくさんいます。
いかに人間関係で皆、疲れ果てていることか、傷を受けている人がいかに多いことでしょう。
過去にも、今にも、未来にも 皆にて謗る人もなく 皆にて褒むる人もなし
(法句経)
お釈迦さまは、他人の評価に幻惑されず、真実の自己を見なさいよ、と教えられています。
(2)自分鏡 自己反省によって知る自己の姿
有名出版社「三省堂」の由来は、「われ日にわが身を三たび省みる」からきているそうです。
人間には道徳的良心があり、それを鏡として反省する動物とも評価されていますが、その「良心」は、正しく自己を映しているのでしょうか。
「この玉の色を見分けた者に、ご褒美を与えます」
乙姫さんが魚たちに尋ねると、黒鯛は“黒です”、サバは“青色”、カレイは“薄茶色”と、皆、答えが異なった。
「どれが本当の色ですか」
声をそろえて乙姫に尋ねると、
「玉は無色透明、皆さんの色が映っただけですよ」
と乙姫さんは笑ったという。
自分の考えや感情の色を全て抜き取って、私たちは何も見られないのではないでしょうか。
なぜなら、私たちは「慢心」の色メガネを死ぬまで外せないからです。
「慢心」とは「自惚れ心」。
「自分に惚れて」自分を見ているのですから、アバタもエクボは当然で、死ぬまで私たちは、自分を毛頭悪く見られないのです。
慢心は絶対外せぬ色メガネだよ、とお釈迦さまは仰います。
自惚れ心を7とおりに分けて、お釈迦さまは「七慢」を説かれています。
(1)慢
自分よりも劣った相手を、情けないやつだと馬鹿にする心。
テストで自分は80点で相手は70点だった時。“どうだ、オレのほうが上だろう”と相手を見下げる心です。そう思うのは当然ではないかと思われるかもしれませんが、相手を踏みつける恐ろしい心です。
(2)過慢
同じ程度の相手なのに、自分のほうが優れていると威張る心。
テストの点数が同じでも、「本当はオレのほうが上なのだ」と自惚れます。
(3)慢過慢
間違いなく相手が優れているのに、素直にそうと認められず「オレのほうが上だ」と思う心。
相手が90点で自分が80点でも、“あいつは親が高い金出して塾に通っている。条件が同じならオレのほうが断然上だ。しかも、確かに勉強はそこそこできるかもしれないが、スポーツはまるでダメ。その点、オレは両方できるし”と、都合のよい理由をいろいろ見つけて相手の上に立とうとします。
(4)我慢
自分の間違いに気づきながらも、どこどこまでも自分の意見を押し通そうとする心。一般に使われる「忍耐」の意味ではない。
(5)増上慢
さとりを開いてもいないのに、さとったと自惚れている心。
6)卑下慢
腰の低さを自惚れる心。「私ほど悪い者はおりません」「こんな未熟者ですが、ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます」と、深々と頭を下げつつ、「どうじゃ、こんなに頭の低い者はおらんだろう」とニンマリします。
7)邪慢
とんでもないことを自慢する心。
窃盗犯が「オレほど素早く他人のものを盗める者はない」と、機敏さを自慢したり、人殺しが残虐ぶりを自慢すると聞くとアキレますが、自分のことは皆、よいようにしか思えないのです。
こんな私たちは、死ぬまで自分の姿を正しく見ることはできません。
では、自己の姿を正しく知るには、どうすればよいのでしょうか。
お釈迦さまは、仏教を聞きなさいと教えられています。
仏教とは、法の鏡だから、真剣に仏教を聞けば、自分の姿がハッキリ知らされてくるのです。
(3)法鏡 真実の自己の姿を映し出す鏡
仏教は法鏡なり。その法鏡とはどんな意味でしょうか。
仏教で「法」とは、三世十方を貫く(いつでもどこでも間違いがない。普遍である)ものです。
国や時代に左右されない、本当の人間の姿をお釈迦さまが説かれた教えが仏教ですから、その仏教を聞いて、真実の自己と対面した時、私たちは「真実の幸せ」になれるのです。
自己を知ることは、本当の幸せの扉を開くたった1つのカギといえましょう。
では、仏教に教えられている人間の真実の姿とは、どのようなものでしょうか。
最新記事 by あさだ よしあき (全て見る)
- お盆に墓参りだけでいいの?今からできる恩返しの方法とは - 2018年8月30日
- 幸せの花ひらく 「因果の法則」を身につける - 2018年6月27日
- 生きる意味は何か|それをブッダはたとえ話で教えている - 2018年6月5日