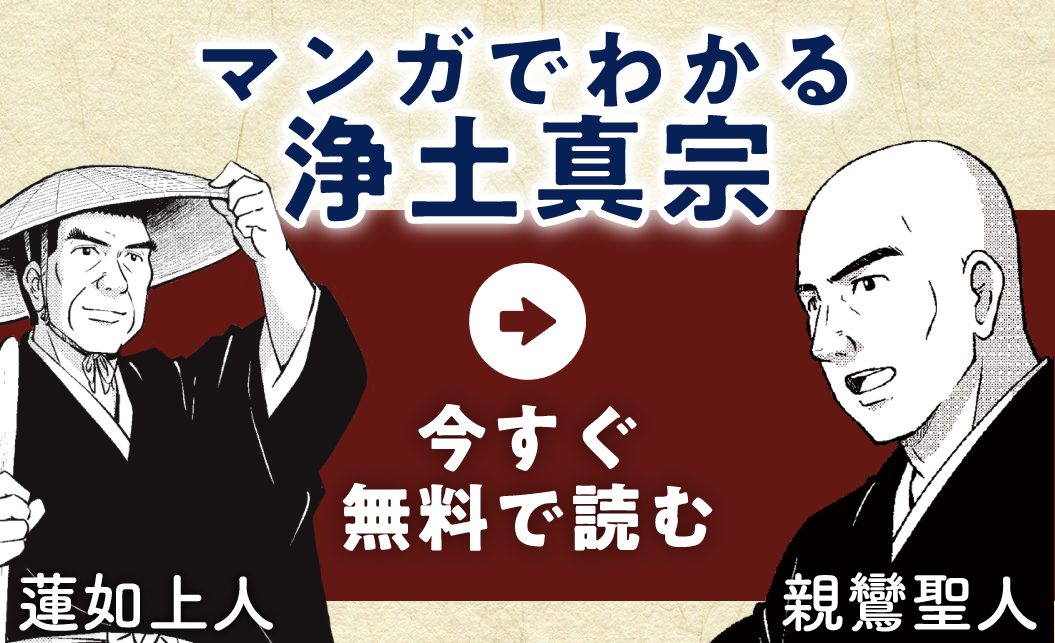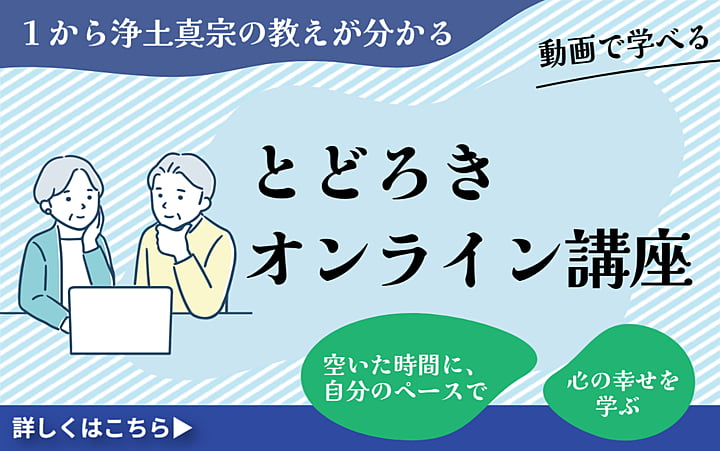我慢は元々違う意味だった?|仏教に教えられる本当の我慢とは
7月3日は生田万の乱があった日ということで、それにちなんでテレビ朝日系列で毎週平日放送中の「グッドモーニング」の中の「ことば検定」で林修先生が「我慢」という言葉について解説していました。
生田万(いくたよろず)の乱とは天保の大飢饉のさなか、豪商や役人の米の買い占めにより米価が急騰したため、天保8年(1837年)6月に国学者の生田万が「もう我慢できん」と現・新潟県柏崎市で貧民救済のために起こした乱です。
(問題)「我慢」、元々の意味は?
- うぬぼれ
- 失敗
- カエルの疑問
答えは、1の「うぬぼれ」です。
我慢というと辛いこと、嫌なことがあっても投げ出さずに耐える意味で使われているので良い言葉のように思えますが、元は仏教から来た言葉です。
ちなみに3番の「カエルの疑問」は「ガマ、ん?」ということで、最近スタッフが最後に「ん?」を付けて誤魔化すことが多いから出したそうです。
仏教では「我慢」を含めて7つの「慢」があると教えられています。
それぞれどういう意味なのでしょうか。
仏教に教えられる我慢
「慢」とは慢心とも言い、うぬぼれ心のことです。
仏教で「我慢」とは、「我」に対する「慢」ですから「自分こそが正しい。他人は間違い」と我を通そうとする心です。
この心のために自分の間違いに気付かず、また気付いていても間違いを認めることができません。
「幼児のケンカは衝突も早いが仲直りも早い。今泣いていたかと思うともう笑っている。
小学生は一度衝突すると二、三日ぐらいは口をきかないが、中学になると一、二週間になる。高校生になると一カ月ぐらい、大学になると五、六カ月はかかる。
社会人ともなると、余程の仲裁人でも入らぬ限り困難である。老人のケンカになると、棺桶に入るまで絶望的となる」
という話がありますが、「老成円熟」という言葉がある一方、「年寄りほど頑固だ」とも、ささやかれます。オレがオレがの「我慢」は、年を増すごとに強くなるのかもしれません。
このような意味から自分自身に固執する=強情であることを表すようになり、やがて「自分の意志を通す強さ」に変わり、安土桃山時代~江戸時代には、「忍耐」の意味になって現代まで続いています。
七慢
お釈迦さまは我慢以外にうぬぼれ心を7つ教えられています。これを「七慢」と言います。
- 慢
- 過慢
- 慢過慢
- 我慢
- 増上慢
- 卑下慢
- 邪慢
の7つです。
慢
「慢」とは、自分より劣った相手をバカにする心です。
例えば学校のテストでいえば自分より点数の低い人を見下す心です。
一見、当然のように思えますが、相手を踏みつける恐ろしい心だとお釈迦さまは教えられています。
過慢
「過慢」とは、自分と同じ程度の相手なのに、自分のほうが優れていると威張る心をいいます。
テストの点が同じであっても、「テスト当日にちょっと体調が悪かっただけ。本当はオレのほうが上だ」とうぬぼれる心です。
慢過慢
「慢過慢」とは、間違いなく自分よりも相手が優れているのに、素直にそうと認められず、自分のほうが上だと思う心です。
そんなおかしなことを思う人があるの?と思われるかもしれませんが、よくあります。
例えばテストの点数が相手が90点で、自分が80点でも、
「あいつは高い金払って塾に通っているからだ、条件が同じならオレが上だ」と思ったり、「あいつは勉強はできるけど、人としての礼儀が全然なってないじゃないか。その点、オレは人間的にもまともだから」などと、自分に都合のいい勝手な理由を見つけて、相手の上に立とうとする心です。
我慢
「我慢」とは、自分の間違いに気づきながら、どこまでも我を押し通そうとする心です。
二人の男が、床にある黒いものを指さして「あ、虫だ」「いや黒豆だ」と言い争っていたところ、モゾモゾ動きだしたので虫だとハッキリしました。
ところが黒豆だと言っていた男は「這っても黒豆なんだ!」と言い張ったそうですが、こんなのを「我慢」といいます。
自分が悪いと分かっていても我慢のせいで謝れない。
一言ゴメンと言えば傷は浅くて済むものを、なかなか素直になれない心があって自分ながらバカだと思いながらも頭が下がりません。
増上慢
「増上慢」とは、さとりを開いてもいないのに、さとったとうぬぼれる心です。自分はもう救われた、さとったのだと錯覚し他人を見下す心です。
卑下慢
「卑下慢」とは、「私ほど悪い者はおりません」「まだまだ未熟者ですが」と深々と頭を下げながら、「どうだ、こんなに頭の低い者はいないだろう」とニンマリする心をいいます。「実るほど頭の下がる稲穂かな」(立派な人ほど偉ぶらず腰が低い)といわれ、そのような人を私たちは尊敬しますが、そんな腰の低い人でも、うぬぼれ心から離れ切ることはできない。
邪慢
「邪慢」は、とんでもないことを自慢する心です。
窃盗犯が機敏さを誇り、人殺しは残虐ぶりを自慢し、自堕落な生活している人が自分のだらしなさに胸を張る。
試験でビリだった人が零点の答案をひけらかす、と聞けばアキレましょうが、「こんな紙切れでオレの価値が測れるか」と、本人は開き直って鼻高々な心です。
これら七つのうぬぼれ心から、私たちはもう離れることができないのだと、お釈迦さまは説破されているのです。
「慢」は煩悩と言われる私たちを煩わせ、悩ませる心の中の1つです。
他の煩悩についてはこちらの記事で紹介しています。
最新記事 by あさだ よしあき (全て見る)
- すべての人に真の元気を与える妙法「南無阿弥陀仏」の偉大な力(前) - 2026年1月12日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(後) - 2025年12月15日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(前) - 2025年11月30日
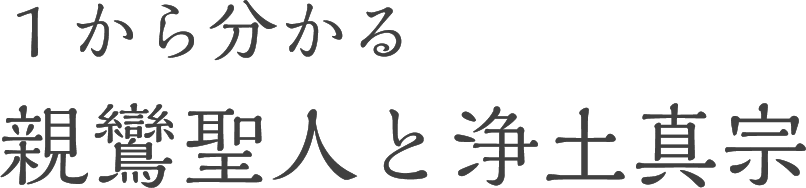

の頭も信心から|あなたは何を信じていますか?-150x150.jpg)