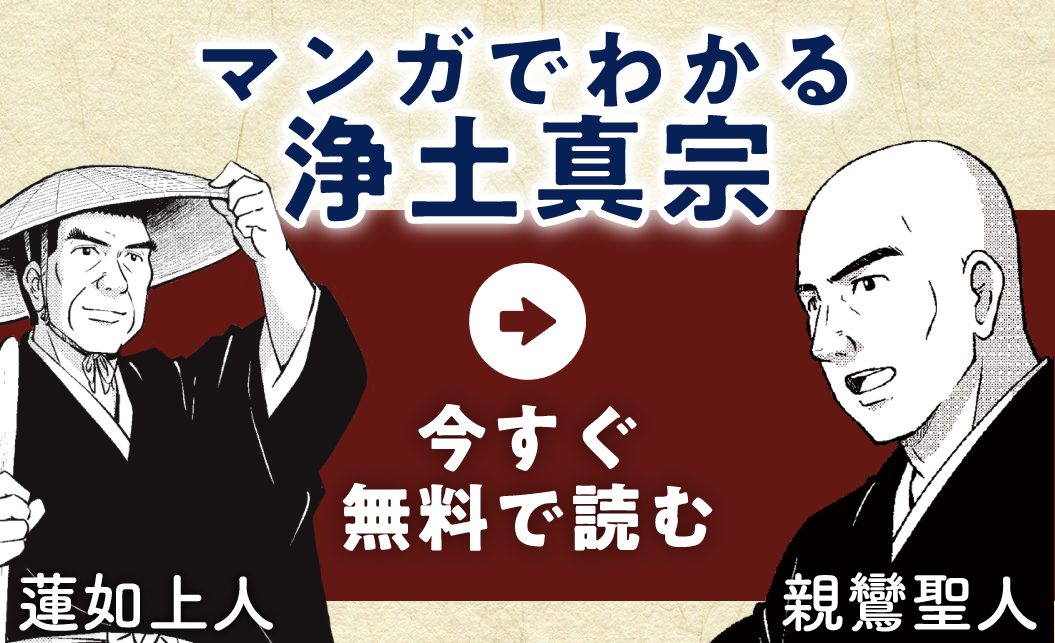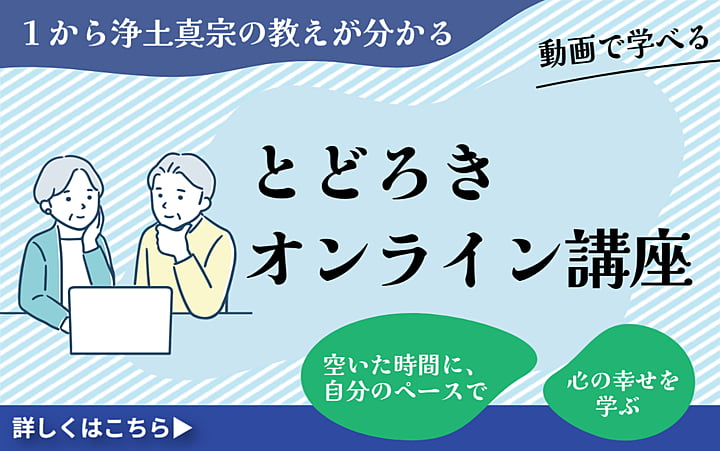大切な人を亡くされたあなたへ|仏教が教える真の人生の意義とは何か(後)
前回はこちら
冒頭の一文
「それ 人間の浮生なる相をつらつら観ずるに 凡そはかなきものは この世の始中終 幻の如くなる一期なり」からお聞きしましょう。
苦しみ漂う人生
まず“人間の浮生なる相をよくよく見てみると”と仰っています。
「浮生」とは「浮いた生」と書くように水面に漂う浮草のような一生のこと。
人間の実相をこう表現されているのです。
どこから来て、どこへ行くのか、
生きる意味も分からぬ根無し草。
何を手に入れてもどこかしら不安で、私たちはひょうたんの川流れのように根拠のない生をフワフワと日々過ごしているのではないでしょうか。
気楽な人生はどこにもなく、皆生きることに必死です。
果たしてどこへ行くのでしょう。
全国紙の人生相談には毎日さまざまな人生模様が描き出されています。
“50代のシングルマザー。寄り道して仕事の帰りが遅くなると同居の母が嫌味を言う。母から自由になりたい”
“40代主婦。幼少時から人見知りの激しい中3の次男が、学校に行きたがらない。高校受験も近いのにどうしたら……”など、人の数だけ苦悩があることが知らされます。
50代の独身女性からはこんな相談も。
「母と弟を相次いで亡くし、一億円以上の遺産を相続した。だが大金を得たと喜ぶより、人生の指針を失ったように感じて戸惑っている。どんな心持ちで暮らせばいいのですか」
“私なら諸手を挙げて歓迎するのに”と思う人も多いでしょうが、大枚を手にすれば自身も周囲も平常心ではいられない。
好事魔多しで 思いもかけぬ事態に襲われることもある。
宝くじの高額当選で人生を誤る人が多いのも生きる目的が分からず、本当の金の使い道を知らないからでしょう。
続いて
「凡そはかなきものは、この世の始中終、幻の如くなる一期なり」。
「始中終」とは始め、中、終わりのこと。
人生まだ始まったばかり、と思っていたのが
すぐ中程に差しかかり、
あれよあれよと終盤へ。
人の一生は幻のようだと仰せです。
40代男性のこんなつぶやきがありました。
「十代の頃、応援していた同い年の女性アイドルが久しぶりにCM出演していたので、オッと思って見てみるとなんと〈白髪染め〉のCM。そうだよな、彼女もデビュー三十年。気だけは若いけど、オレも……」
夢の如く過ぎ去る時間
「一生過ぎ易し」
人生の速さを 古今の人々はさまざまに表現しています。
有名な能の『邯鄲(かんたん)』は中国の古典に題をとった演目。
「一炊の夢」ともいわれる故事です。
―――――
田舎の青年・盧生が人生に迷い、有名な僧侶を訪ねて教えを請おうと旅に出た。
途中、邯鄲という町の宿屋で休憩していると、女主人が仙人からもらったという枕を出して、粟の炊ける間に一休みするよう勧めた。
やがて眠りかけた盧生を楚国の役人が迎えに来る。
どうしたわけか、帝が彼に譲位したいという。
驚きつつも彼は王位に就く。
有為転変も味わいながら、栄耀栄華を極め、気づけば五十年の歳月。
波乱万丈の一生だったなあと思ったその時、女主人に起こされた。
粟飯がようやく炊き上がったということだった。
―――――
終幕─皆行く道
「我や先、人や先、今日とも知らず、明日とも知らず」
俳優のIさんが五十四歳の若さで亡くなりました。
演劇に情熱を傾け、男気ある言動が人気でしたが死の一カ月前、ガン闘病を告白する記者会見には痩せ衰えた彼の姿が。
かつての精悍な風貌は消え、人前もはばからず
「悔しい、悔しい」
と涙を流すインタビューが胸を打ちました。
若い終幕に惜しむ声は絶えませんが、遅かれ早かれ皆行く道であります。
しかも人間は貪欲(欲)、瞋恚(怒り)、愚痴(ねたみ そねみ)の三毒の煩悩にまみれ、生きるためとは言いながら、数限りない殺生を繰り返している。
誰もが抱え切れぬ悪業を背負って生きているのです。
人生、夢幻の如し。
「朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり」と知らされれば「私の後生はどうなるのか?」と問わずにおれなくなるのです。
弥陀を一心にタノメ
この『御文』の最後に
「誰の人も、はやく後生の一大事を心にかけて、阿弥陀仏を深くたのみまいらせて、念仏申すべきものなり」
と 蓮如上人は、真の生きる目的を教えられています。
「誰の人も」とはすべての人のこと。
「はやく」は明日なき命の私たちだから一日も片時も急げと言われています。
「後生の一大事」とは生ある者 必ず死す。死んでどこへ行くのか ハッキリしないこと。
後生と無関係な人は一人もありません。
万人共通の一大事であり、これを生死の一大事ともいいます。
この生死の一大事を解決し
「どんな人も 必ず極楽浄土に往生させてみせる」
と誓われているのは大宇宙最高の仏さま、無上仏ともいわれる阿弥陀仏だけなのです。
その阿弥陀仏の誓い、約束を 蓮如上人はこう教えられています。
「弥陀仏の誓いましますようは 『一心一向にわれをたのまん衆生をば 如何なる罪深き機なりとも救いたまわん』といえる大願なり」
(御文章二帖目九通)
「すべての人よ、一心に我をたのめ、どんな悪人も、必ず絶対の幸福(往生一定)に救い摂る」
との偉大な誓願であります。
蓮如上人が『白骨の章』の最後に
「阿弥陀仏を深くたのめ」
と言われているのは、私の生死の一大事はこの阿弥陀仏の本願によらねば救われないからなのです。
弥陀たのむ一念に往生一定、絶対の幸福に救い摂られたならば来世は必ず極楽浄土に往って、弥陀同体の仏に生まれることができる。
これこそ人界受生の本懐(人生の目的)なのだから、今真剣に仏法を聞けよと教導されているのです。
タノム=あてにする力にする
では肝心の「弥陀たのむ」とはどんなことか。蓮如上人の『御文章』には 至る所に
「弥陀をタノメ」
「弥陀をタノム」
と仰っています。
これは大変重要な、しかも誤解されているお言葉です。
「弥陀をタノメ」
「弥陀をタノム」
「弥陀をタノミ」
をほとんどの人は、他人にお金を借りに行く時のように頭を下げて
「阿弥陀さま どうか助けてください」
とお願いすることだと思っています。
ところが蓮如上人の教えられる
「弥陀をタノメ」
は 全く意味が異なりますから注意しなければなりません。
古来 「タノム」という言葉に「お願いする」という祈願請求の意味は全くありませんでした。
今日のような意味で当時この言葉を使っている書物は見当たりません。
それが「お願いする」という意味に使われるようになったのは後世のことなのです。
「タノム」の本来の意味は 「あてにする、憑みにする、力にする」ということ。
蓮如上人の仰る
「弥陀をタノム」
は 阿弥陀仏をあてにする、憑みにする、力にするという意味なのです。
もし蓮如上人が
「阿弥陀仏にお願いせよ」
と仰ったのなら
「弥陀にタノム」
と書かれるはず。
ところがそのような『御文章』は一通もありません。
常に
「弥陀をタノメ」
「弥陀をタノム」
と「弥陀を」と仰って 「弥陀に」とは言われていません。これらでも明らかなように
「弥陀をタノメ」
「弥陀をタノム」
は 祈願請求の意味ではないのです。
浄土真宗で「タノム」を漢字で表す時は
「信」とか
「帰」で表します。
「信」はお釈迦さまの本願成就文の「信心歓喜」を表し、「帰」は天親菩薩の『浄土論』の「一心帰命」を表したものです。
阿弥陀仏に信順帰命したということは、弥陀の本願が「あてたより」になったことです。
ゆえに親鸞聖人は
本願他力をたのみて自力をはなれたる これを『唯信』という(唯信鈔文意)
本願他力があてたよりになって、自力の心のなくなったのを唯信という。
と仰せになっています。
蓮如上人も
「一切の自力を捨てて、弥陀をタノメ」
と仰っています。
「弥陀をタノメ」
とは自力の計らいを捨てよということです。
一切の計らいが自力無功と照破され
「弥陀の五劫思惟は私一人のためだった」
と明知したのを
「弥陀をタノム」
と言われているのです。
蓮如上人の
「自力を捨てて、弥陀タノム」
は、昿劫流転の迷いの打ち止めであり、他力永遠の幸福に輝く時です。
だから他力になるまで他力を聞くのだと教えられています。
弥陀の救いは「聞く一つ」。
弥陀をタノム一念に本願を聞きひらいて、往生一定の身にさせていただきましょう。
最新記事 by あさだ よしあき (全て見る)
- すべての人に真の元気を与える妙法「南無阿弥陀仏」の偉大な力(前) - 2026年1月12日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(後) - 2025年12月15日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(前) - 2025年11月30日
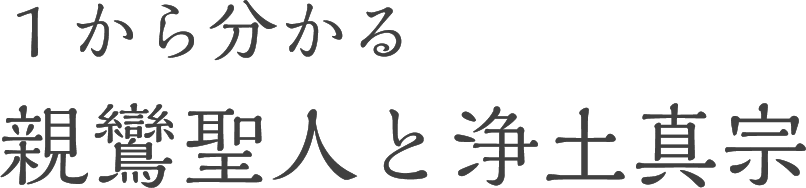

の頭も信心から|あなたは何を信じていますか?-150x150.jpg)