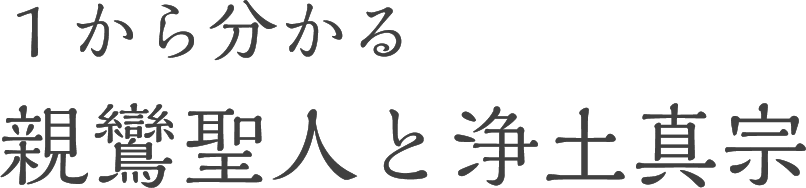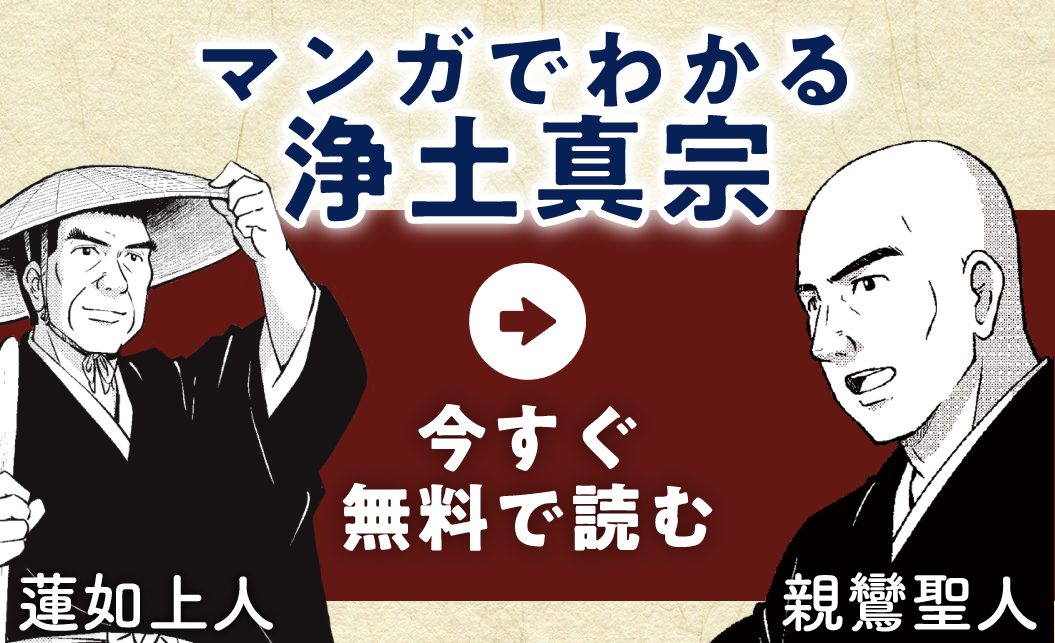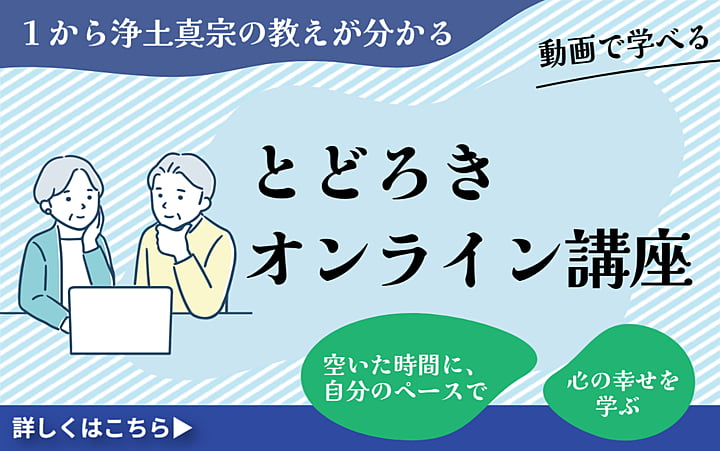タイの僧侶は肥満・高血圧の人が多い?|布施・托鉢は誰のためにするものか
「僧侶やお坊さんの体つきを思い浮かべてみてください」と言われたら、どのような体型を思い浮かべるでしょうか。
中には、ふくよかの方もありますが、たいていは中肉中背を思い浮かべると思います。
しかしタイの僧侶はそうではないようです。
タイの大学が2016年に僧侶を対象に実施した調査によると、約48%が肥満、約42%が高血圧と診断されました。
タイの僧侶といえば日本の僧侶とは違ってオレンジ色の衣を着て、修行したり托鉢したりしているイメージがありますので、肥満・高血圧の人が多いと聞くと驚くかもしれません。
なぜタイの僧侶はそんなに肥満・高血圧の人が多いのでしょうか。
それは「布施」に理由があるのです。
布施とはなにか
仏教で布施と言われるのはどのようなことでしょうか。
布施とは「布を施す」と書きますので何かを施す・与えることだろうと思いますが、ただ物やお金を施すことだけでなく他人に親切をすることを言います。
困っている人のためにお金や物を与えるのも布施ですが、お金や物を持たない人でもできる七つの施しがあるとお釈迦様は教えられています。
これを「無財の七施(むざいのしちせ)」と言います。
- 眼施(げんせ)―優しい眼差しで人に接すること
- 和顔悦色施(わげんえっしょくせ)―優しい微笑を湛えた笑顔で人に接すること
- 言辞施(ごんじせ)―優しい言葉をかけること
- 心施(しんせ)―心から感謝の言葉を述べること
- 身施(しんせ)―体を使って、人のため社会のために働くこと。無料奉仕
- 床座施(しょうざせ)―場所や席を譲り合うこと
- 房舎施(ぼうしゃせ)―訪ねてくる人があれば一宿一飯の施しを与えること
これらの布施は、心がけさえあれば誰でもできる布施・親切です。
お釈迦様が布施をすすめられたのは、よい種まき・善だからです。
仏教の根幹である因果の道理という教えがあります。
善因善果
悪因悪果
自因自果
良いことをすれば良い結果がやってくる。
悪いことをすれば悪い結果がやってくる。
自分がやったことが自分に結果として返ってくる。
ですから、「布施はよい種まきだから、他人に布施をすればやがて必ず自分に返ってきて、布施をした人が幸せになれますよ。だから布施をしましょう」とすすめられるのです。
布施は断れない
この「布施」とタイの僧侶に肥満・高血圧が多い事実とどんな関係があるのでしょうか。
僧侶には托鉢(たくはつ)という修行があります。
鉢を持って施しを受ける行のことで、その受けた施しによって生活しています。タイの僧侶は葬式や法事で生活しているのではありません。
タイの人は仏教を尊いものと思っている人が多く、僧侶というだけで敬われます。
日本の私たちですと、托鉢だけで生活していけるのだろうかと心配してしまいますが、タイの僧侶は、多くの人から施しを受けるため、食べるものに困らないそうです。
この托鉢には大事なルールがあります。
それは「施されたものはすべて有り難く頂かなければならない」ということです。
「僧侶は尊い方だから布施をしよう」と思う人で溢れているタイでは、托鉢をすると非常に多くの食べ物も受け取ることのですが、施される食べ物は、野菜スープやサラダなどをあまりなく、砂糖菓子や炭酸飲料、スナック菓子などを中心に布施がなされるため、ルールに従って、それらを毎日たくさん頂いていると、どうしても肥満・高血圧の人が多くなってしまうのです。
布施の相手は田んぼのようなもの
なぜ「施されたものはすべて有り難く頂かなければならない」ルールがあるのでしょうか。
仏教では、布施の相手を田んぼに例えられていることから知って頂きたいと思います。
布施、施しは、誰にしても、よい種まきになるのではありません。
ギャンブル好きな人にお金を渡せば、ますますギャンブル依存になってしまいます。泥棒の手伝いをすれば、被害を受ける人が増えてしまいます。
では、どんな人に布施をすれば、すばらしい種まきになるのか。
お釈迦様は、田んぼに例えられて、三田(さんでん)と三通りの人を教えられています。
三田とは、敬田(きょうでん)、恩田(おんでん)、悲田(ひでん)です。
敬田 敬うべき方。
恩田 恩を受けた方。
悲田 災害などで苦しむお気の毒な方。
田んぼに例えられるのは、田んぼにモミ種を蒔くとその時は手持ちの米が減ってしまいますが、収穫の時には何倍もの結果となって返ってくるように、布施は施した時には自分の分が減ってしまうように思いますが、後に大きな結果となって返ってくるからです。
僧侶が托鉢をするのは、自らが敬田の田んぼとなるためです。
自らが田んぼとなって布施を受ける。
そうすれば布施をした人に幸せな結果が訪れる、人々を幸せにするために行うのが托鉢です。
ですから布施を断ることは相手が幸せになる機会を奪うことになりますから、布施を断ってはいけないという大事な決まりがあるのです。
そうは言っても、さらに肥満で血圧が上がりますと、命にかかわりますので、食べるものを制限して健康になろうと努力する僧侶も増えているそうです。
仏教で教えられる布施・托鉢とは、誰のために行うのかを知って、お互い、三つの田んぼに、幸せの種をまいていきたいと思います。
布施に関してこちらの記事でより詳しく解説していますのでぜひご覧ください。
最新記事 by あさだ よしあき (全て見る)
- すべての人に真の元気を与える妙法「南無阿弥陀仏」の偉大な力(前) - 2026年1月12日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(後) - 2025年12月15日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(前) - 2025年11月30日