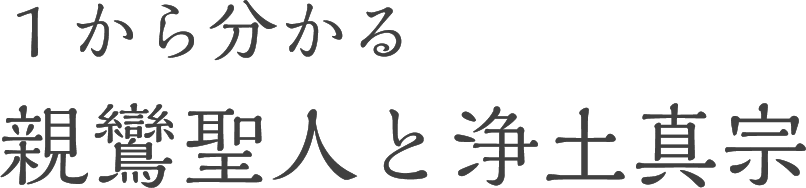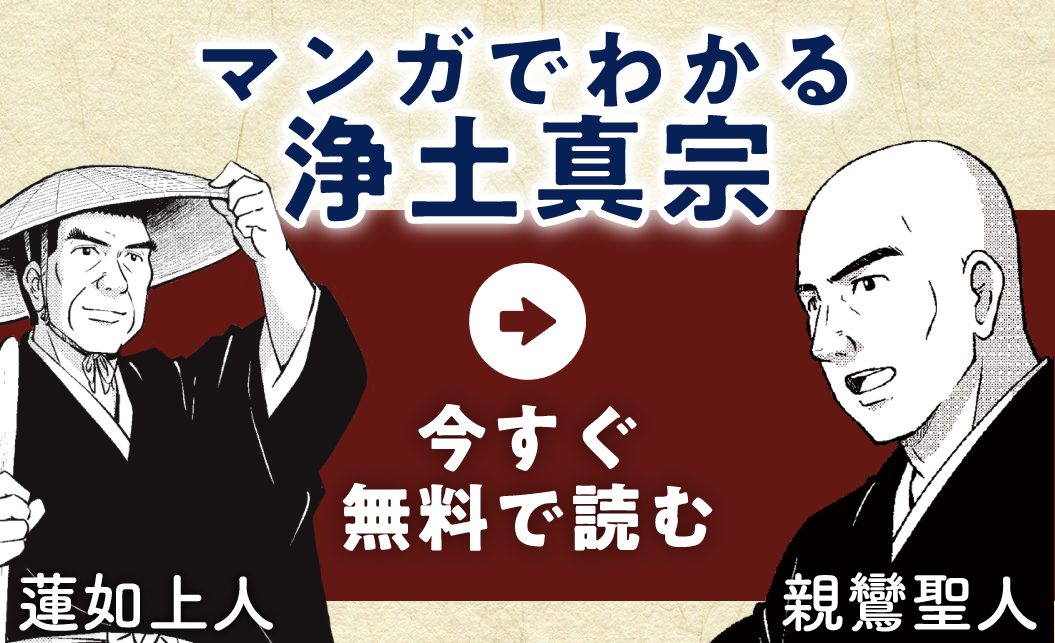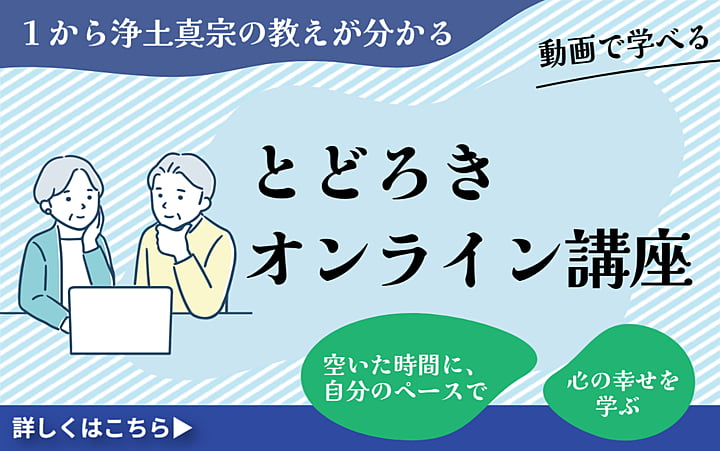浄土教を弾圧した上皇が浄土教に転向?|仏教と上皇の深い関係
元号が平成から令和に代わり、平成の天皇は上皇となりました。
「上皇」とは天皇が退位したあとの呼び名です。正確には太上天皇と言い、その略称が上皇です。
江戸時代の光格天皇(在位:1780年1月1日 – 1817年5月7日)を最後に上皇になる天皇がなかったため「上皇」という言葉にしっくりこないですが、歴史の教科書にはよく出てくるので聞いたことがある方も多いでしょう。
歴史上126人の天皇のうち、上皇になったのは60人なので歴史的に見れば珍しくはありません。
さらにその中で35人は出家して法皇となっています。
最後の法皇は江戸時代の霊元法皇です。
ですから出家した上皇のほうが、出家しなかった上皇よりも多いことになります。
日本神道の象徴であった天皇が、退位後に仏教に転向し出家するのは栄枯盛衰を感じるからでしょうか。
そのうちの一人が、鎌倉時代に法然上人が浄土宗を開いて、多くの人が阿弥陀仏の救いを聞き求める中、その法然上人を弾圧し、流刑にした上皇が後鳥羽上皇です。
しかし後年、後鳥羽上皇は浄土教の教えに目覚めました。
後鳥羽上皇とはどのような人だったのでしょうか。
承元の法難
後鳥羽上皇は源平の争いの中で4歳で即位し、19歳のときに土御門天皇に譲位して上皇となりました。(在位:1183年-1198年)
それから23年間、上皇として院政を敷きます。
院政とは上皇が天皇に代わって政務を直接行う形態の政治のことです。
上皇のことを「院」とも呼んだので院政と言われます。
その院政の最中の承元元年(1207年)後鳥羽上皇が熊野に参詣している最中に、上皇が寵愛していた女官と法然上人の弟子が密通し、さらに出家させてしまいました。
その話を熊野詣でから帰ってきた後鳥羽上皇が聞いて激怒し、また浄土宗の繁栄を妬む天台宗、真言宗などの諸宗からの訴えもあり、ついに浄土宗の解散、念仏布教の禁止、法然上人の土佐への流罪、主だった弟子の死罪あるいは流罪が決まったのです。
これを承元の法難と言います。
法然上人の弟子であった親鸞聖人も初めは死刑の判決だったのですが、法然上人の信奉者であり、親鸞聖人の義理の父である九条兼実の計らいで越後に流刑となりました。
親鸞聖人は尊敬する法然上人を無実の罪で流刑にし、法友たちを死刑流刑にした後鳥羽上皇以下大臣たちに対して猛烈に怒られ、主著の教行信証にはこう書かれています。
「主上・臣下、法に背き義に違し、忿(いかり)を成し、怨(あだ)を結ぶ。これによりて、真宗興隆の太祖源空法師、ならびに門徒数輩、罪科を考えず、猥(みだりがわ)しく死罪に坐(つみ)す。或は僧の儀を改め、姓名を賜うて遠流に処す。予はその一なり」
天皇も臣下も、真の大法に背き、正義に違い、みだりに無法の怒りを起こし、恨みを結び、ついに浄土真宗を興隆してくだされた法然上人をはじめ、門下の優れた人々を罪科のいかんを考えもせず、無茶苦茶に死罪を決行し、また、僧侶の資格を剥奪して遠国に流したのだ。迫害するのは権力の本性とはいいながら、何という無法であろう。親鸞もその流刑に遭った一人である。
しかもその直前の文章は、初めは誰に対しての怒りかぼかした書き方をされていましたが、後鳥羽上皇の死の知らせを聞かれたあとに「ここをもって、興福寺の学徒、太上天皇[後鳥羽院と号す]」と[後鳥羽院と号す]を付け加えられています。
これが親鸞聖人67歳頃のことですから親鸞聖人の怒りは終生変わらなかったと言えましょう。
流刑後の後鳥羽上皇
その後、後鳥羽上皇は41歳のときに承久の乱を起こします。
当時日本の政権は西の朝廷と東の幕府との2つに分かれており、それを忌々しく思っていた後鳥羽上皇は3代将軍源実朝が暗殺され北条氏が跡を継いだと聞き、これぞ朝廷が力を取り戻す絶好のチャンスとばかりに幕府を滅ぼそうと兵を挙げます。
しかし結果は惨敗。
後鳥羽上皇は戦犯として隠岐島(島根半島の北方約50kmにある島)に流されることになりました。
流刑後の後鳥羽上皇は19年間隠岐島で暮らして60歳で生涯を閉じました。
国の最高権力者が一転して流刑の罪人になったことで世の無常を感じたのか、以前から交流のあった聖覚法印(せいかくほういん)から阿弥陀仏の本願を聞き、浄土往生を願うようになりました。
聖覚法印は法然上人の弟子で、親鸞聖人にとっては兄弟子に当たる方です。
後鳥羽上皇の最期の著作『無常講式』には
契りても、なお契るべきは菩薩聖衆の友、憑みても、なお憑むべきは弥陀本誓の助けなり。
ただ戒とおよび施と放逸せざると、今世後世に伴侶になる。この諸の功徳に依て、願はくば命終時において、無量寿仏 無辺功徳の身を見たてまつらん。我および余に信ずる者、既に彼の仏を見たてまつりおわりて、願わくは離垢の眼を得て、安楽国に往生せん。南無阿彌陀佛
と書かれており、浄土教を弾圧した後鳥羽上皇も最後は阿弥陀仏の救いを求めて死んでいったことがわかります。
この『無常講式』の文章を一部引用して作られているのが、浄土真宗の葬式のときによく読まれる蓮如上人の『白骨の章』です。
白骨の章についてはこちらの記事をご覧ください。
最新記事 by あさだ よしあき (全て見る)
- すべての人に真の元気を与える妙法「南無阿弥陀仏」の偉大な力(前) - 2026年1月12日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(後) - 2025年12月15日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(前) - 2025年11月30日