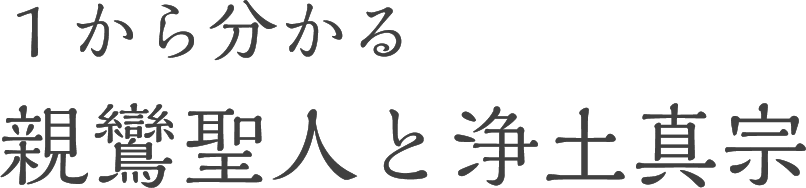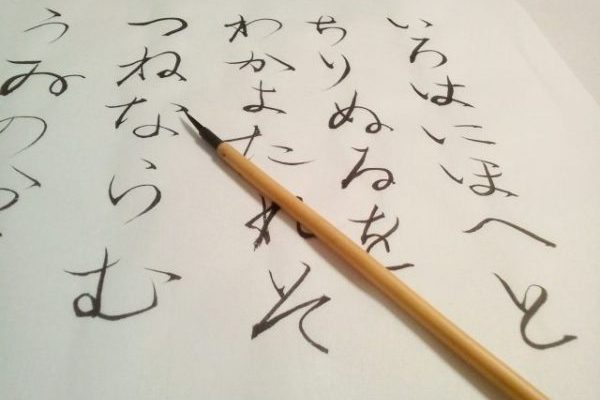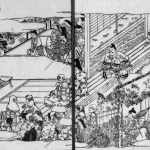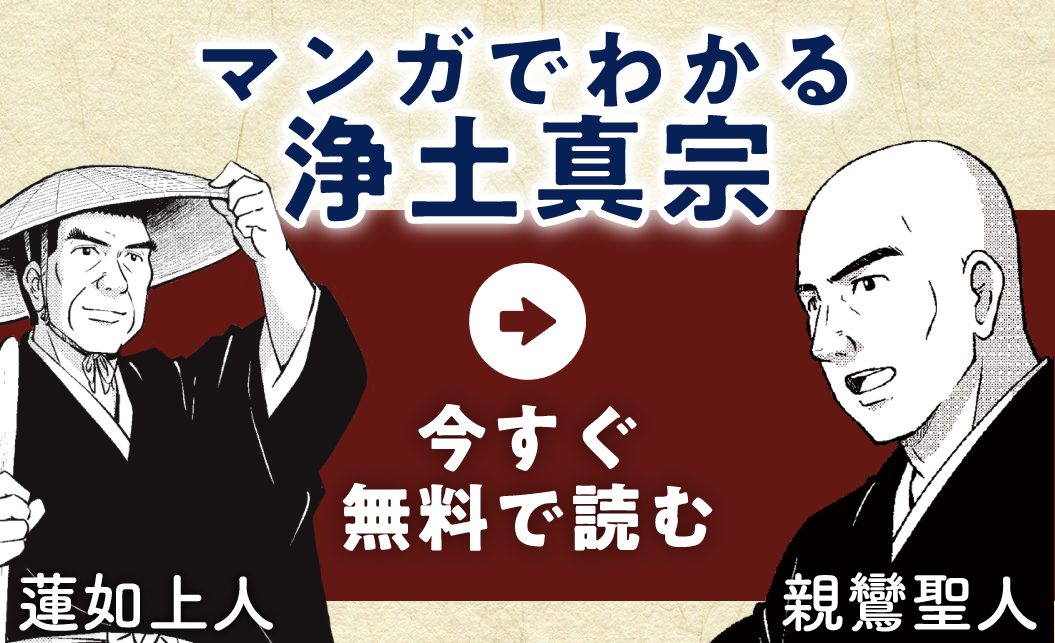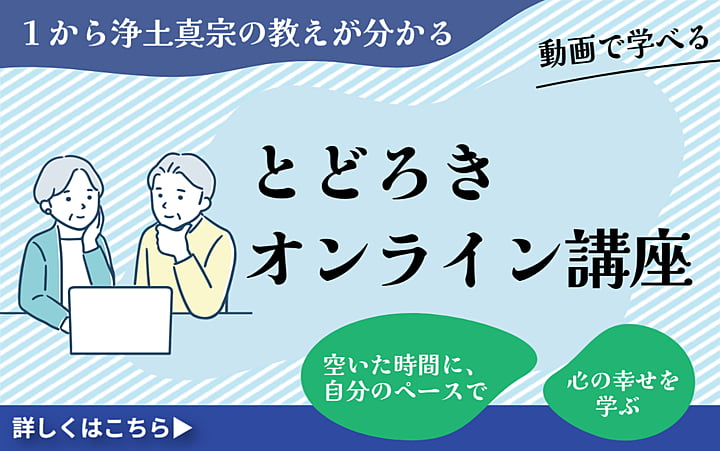知ってそうで知らない「いろは歌」に隠された幸せへの道
いろはにほへと ちりぬるを わかよたれそ つねならむ
文豪・芥川龍之介は『侏儒の言葉』の中に、“いろは短歌には、人生における必要なことは全て教えられている”と書き残しています。
「人生に必要なこと」って何でしょう。
今回はこの「いろは歌」47文字に秘められた人生に必要な「幸福のカギ」を解説します。
「いろは歌」には「人生に大切なこと」が教えられている
昔の寺子屋で、読み書きを教える時に使われた「いろは歌」は、平仮名47文字を、重なることなく並べて歌にしたというものです。
古くから伝わるこの「いろは歌」に、実は仏教の深い教えが込められていることは、案外知られていません。
いろはにほへと ちりぬるを
わかよたれそ つねならむ
うゐのおくやま けふこえて
あさきゆめみし ゑひもせす
漢字を当ててみると、ぼんやりと意味が浮かび上がってきますね。
色は匂えど 散りぬるを
わが世誰ぞ 常ならむ
有為の奥山 今日越えて
浅き夢見じ 酔いもせず
「色」とは、桜の花のことですから、爛漫と咲き誇る桜花も、あっと言う間に、1枚残らず散ってしまうことを、一句目で詠われています。
二句目では、桜の花と同じように、この世のどんな成功者も、一体、誰が、いつまでも変わらずにその栄光を保ち続けられるだろうか、と世の無常を訴えています。
三句目と四句目は、その無常の世を悲しみ嘆く私たちが、生きている時に、その苦しみを解決し、迷いの夢から覚めて絶対の幸福になれるという、仏の教えが示されているといわれます。
このいろは歌の元になったという、お経の言葉が、次の漢字16字です。
諸行無常
是生滅法
生滅滅已
寂滅為楽
この言葉は、お釈迦さまが、雪山童子という修行者であった時に、命と引き替えにしてさとられた真理と伝えられています。
かつて国語の教科書にも、「修行者と羅刹」という題名で掲載されていた、次の有名なエピソードです。
修行者と羅刹
雪山で一人、真の幸福を求めて、苦行に打ち込む修行者がいた。
すると、風に乗ってどこからか、尊い言葉が聞こえてきた。
「諸行無常 是生滅法」
(咲いた花もたちまち散り、人は生まれてもやがて死ぬ。無常は全てのものの免れぬ運命である)
そのさとりの言葉を聞いた修行者は、喉の渇きにあえいでいる時に、清らかな水を得たように、大きな喜びを感じた。
しかし、辺りを見回して声の主を探すが、人影は見えない。今のはさとりの半偈(真理の半分)。残りの真理の言葉を聞きたいと、探し回った揚げ句、突如、崖の上に恐ろしい鬼の姿をした羅刹を見た。
「大士よ。今、尊い言葉を発せられたのは、あなた様ではありませんか。残りの半偈を聞かせていただき、どうか、私にさとりを開かせてください」
すると羅刹は、
「わしは何も知らない。ただ、あまりに空腹で、うわごとのように何か言ったかもしれぬ。しかし、もう腹が減って、何も言う力がないのだ」
とつれない言葉を吐いた。
「では、あなた様のために食べ物を用意いたしますから、教えてください」
重ねて懇願すると、羅刹は驚くべき無理難題を言い放つ。
「それはとてもおまえに用意できるものではない。私は、生きた人間の血のしたたる肉しか食わないのだ」
意外にも修行者は少しも驚かず、
「分かりました。では、残りの言葉を聞かせていただければ、私のこの肉体を、あなたに差し出しましょう」
と真剣な面持ちで答え、羅刹に敬礼して教えを乞うた。
羅刹は、おもむろに口を開いた。恐ろしい形相から、どうしてこんな声が出るのかと思われるほど、それは美しい声であった。
「生滅滅已 寂滅為楽」
修行者は、その意味をさとって心に大きな喜びを得た。
後の世の人のために、そのさとりの言葉を石や木に刻みつけ、やがて、するすると近くの木に登ると、そのてっぺんから羅刹に向かって、ひらりと身を投げた。
真っ赤な口を開いた羅刹は、刹那に端厳な帝釈天と姿を変え、修行者を受け止めると、恭しく地上に降ろして合掌した。
「善いかな善いかな、その覚悟あってこそ、あなたはさとりを得ることができたのです」
妙華が舞い降り、修行者の菩提心を祝福したのである。
お釈迦さまは、このお言葉で、一体、何をさとられたのでしょうか。
仏教で、さとりといわれるのは、大宇宙の真理をさとること。
真理といっても、数学的真理、科学的真理などもありますが、仏教が説く真理とは、「すべての人が本当の幸せになれる真理」のことです。
この16文字には、どうしたら、私たちが本当の幸福になれるのか、その道が教えられているのです。
では、その真理を明らかにいたしましょう。
「無常を観ずるは菩提心の一なり」
まず、「諸行無常」の「諸行」とは全てのもの、「無常」とは、常がなく、変わり続けていることです。
この世のどんなものも、変化している。
私たちが、どんなに大事にしているものも、愛する人も、形あるものは必ず壊れていく定めにあります。
これが、生じたものは必ず滅する、万古不変の真理であることを、
「是生滅法(是れ生滅の法なり)」
と教えられているのです。
「そんなこと考えていたら、暗くなるだけ」
「悲観的なことばかり聞かされるから、仏教は嫌い」
と敬遠する人もあるかもしれません。
しかし、例えば私たちは、健康診断を受けるでしょう。
悪いところが見つかったらイヤだから、後回しにしたい気持ちにもなりますが、検査を受けて初めて、不調の原因がはっきりし、治療方法を明確にすることができます。
健康を取り戻すには、肉体の状態をありのままに知ることが大切なのです。
地震で家が倒壊しないだろうかと心配な人も、耐震性の検査を受けて、補強工事を行えば、安心できます。
いろは歌は、まず、最初の二行で、古今東西変わらぬ、諸行無常の現実を明らかにし、それから、不変の絶対の幸福になれる道を示しているのです。これを、仏教では、
「無常を観ずるは菩提心の一なり」
と教えられています。
観ずるとは、ありのままに見つめること、菩提心とは、変わらない本当の幸せ、絶対の幸福のことです。無常を無常と見つめることが、絶対の幸福への第一歩なのです。
逆に、無常の現実には目を塞いで、幸せだけを求めたらどうなるでしょうか?
それでは、幸せのまっただ中に、思わぬ落とし穴にはまり込んでしまうよと仏教では警告されています。
大きな幸せのあとに悲しみがやってくる
春の新入社員を見ていると、初めて社会に出て、仕事の厳しさや素晴らしさを学んだ当時を思い出し、心が洗われる気持ちにさせられます。
経験を積めば積むほど、上司や部下、いろいろな仕事相手との信頼関係が深まって、やりがいも出てくるもの。
責任ある立場に立てばなおさら、多くの人から慕われるようになるでしょう。
ところが、いつまでも仕事を続けるわけにはいきません。
若手を伸ばすためにも、引き際を考える年齢になると、それらの仕事仲間と別れねばならないという、寂しさが心の中を吹き抜けていきます。
ある会社の重役が、毎年1000通以上の年賀状を受け取っていたが、引退した途端、数えるほどになってしまい、大変なショックを受けた。多くの人から慕われていた人ほど、寂しさは深まるのでしょう。
会社のために、後継のためにも、それでいいんだと、自分を納得させようとしても、割り切れないわびしさ。
仕事に没頭した人ほど、心の中にポッカリと開いた穴が大きくなるのは、なんと皮肉なことでしょうか。
子供が結婚して自分から去ったあと、うつ病になる女性が多く、「空の巣症候群」と名づけられています。別離がそれだけつらいのは、おなかを痛めた子は命だからでしょう。
「山高ければ谷深し」
といわれるように、目に入れても痛くない、かわいい子であればあるだけ、別れの寂しさは耐え難いものです。
大きな幸せを味わったあとには、悲しみが必ずやってくる。
「会者定離」
(会う者は、離れるに定まれり)
とも説かれるように、出会いの喜びには、必ず、別れの悲しみが付きまとう。
「なぜ私は苦しまねばならないのか?」
それは、私が幸せだったからなのです。
「愛とは巨大な矛盾であります。それなくしては生きられず、しかもそれによって傷つく」
古今の哲学者たちも、この世の幸せの実態を嘆かずにいられません。
悲しみの涙の一滴一滴が、感謝の涙に変わる
「いろは歌」の後半には、こんな悲しみに満ちた世界を「有為の奥山」と言われ、その悲しみを、「今日越えて」と、生きている時に、乗り越えることができると説かれています。
前半の「諸行無常 是生滅法」の真理は、この本当の幸せに導くために説かれているのですが、そのことを知らない人にとっては、仏教は暗くて嫌だと思われるのでしょう。
「生きている時に、ハッキリと絶対の幸福になれる」
これが、親鸞聖人の教えの一枚看板といわれる「平生業成」です。
「平生」とは、死後ではない、生きている現在のこと。「業」とは変わらない絶対の幸福。「成」とは、達成できるということです。
その教えのとおりに、絶対の幸福になった時、
「憂きことも 悲しきことも ご方便」
(大切なものを失った悲しみは、この永遠の幸せに導くためのご方便〈手段方法〉であった)
と知らされるのです。
お釈迦さまの時代にも、別れの悲しみを、仏教によって乗り越え、本当の幸せに導かれた、一人の女性のエピソードが残されています。
お釈迦さまとキサーゴータミー
お釈迦さまのおられたインドに、キサーゴータミーという麗しい女性がいた。
しかし、命より大切に育ててきたわが子が、病で急死した。狂わんばかりに愛児の亡骸を抱き締め、この子を生き返らせる人はないかと尋ね回った彼女は、幸いにもお釈迦さまに巡り会う。
泣く泣く、子供の蘇生を願う母親に釈迦は、こう言われた。
「あなたの気持ちはよく分かる。いとしい子を生き返らせたいのなら、今まで死人の出たことのない家から、ケシの実を一つかみもらってきなさい。すぐにも子供を生き返らせてあげよう」
それを聞くなり彼女は、町に向かって走った。
しかし、どの家を訪ねても、「昨年、父が死んだ」「先日、子供に死別した」という家ばかり。
ケシの実はどの家にもあったが、死人を出さない家はどこにもなかった。
夕闇が町を包む頃、駆けずり回った彼女は、もはや歩く力も尽き果て、トボトボとお釈迦さまの元へ戻っていった。
「お釈迦さま、死人のない家はどこにもありませんでした。私の子供も死んだことがようやく知らされました」
「そうだよキサーゴータミー。人は皆死ぬのだ。明らかなことだが、分からない愚か者なのだよ」
「本当にバカでした。こうまでしてくださらないと、分からない私でございました。こんな愚かな私でも、救われる道を聞かせてください」
彼女は深く懺悔し、仏教を聞き求めて幸福になったといわれます。
「夢の世を あだにはかなき 身と知れと 教えて還る 子は知識なり」
知識とは、仏教の先生のことです。
もしあの子が、この世の無常を、身をもって教えてくれなければ、無常を無常と知らず、真実の幸せを求めようともしなかったであろう。
そう考えれば、わが子は、私を真実の幸福に導いてくだされた師であったのだと、ゴータミーは感涙にむせんだに違いありません。
親鸞聖人も、4歳でお父様、8歳でお母様を亡くされ、その別離の悲しみを縁に、仏道を求められ、29歳の時に、絶対の幸福に救い摂られました。
喪失の淵に悲しみ、途方に暮れる人も、その涙の一滴一滴が、感謝の涙に変わる時が来る。
だから、くじけず生き抜いて、絶対の幸福を教えた仏教を聞き求めましょうと、温かいエールを送っているのが、「いろは歌」に込められた仏教精神なのです。
まとめ
- 「いろは歌」には、「諸行無常」の現実と、生きている時に「絶対の幸福」になれる 「平生業成」の教えが示されています。
- 諸行無常が仏教で説かれるのは、いたずらに暗く沈ませるためではなく、真の幸福に導くためですから、「無常を観ずるは菩提心の一なり」と教えられます。
- 幸せであればあるだけ、喪失の悲しみ、怒りが大きくなってしまうのが、私たちの求めている幸せです。
- 大事なものを失って悲嘆に暮れることがあっても、それを縁に仏教を聞けば、絶対の幸福に救われ、流した涙の一滴一滴が、喜びと感謝の涙に変わります。
最新記事 by あさだ よしあき (全て見る)
- お盆に墓参りだけでいいの?今からできる恩返しの方法とは - 2018年8月30日
- 幸せの花ひらく 「因果の法則」を身につける - 2018年6月27日
- 生きる意味は何か|それをブッダはたとえ話で教えている - 2018年6月5日