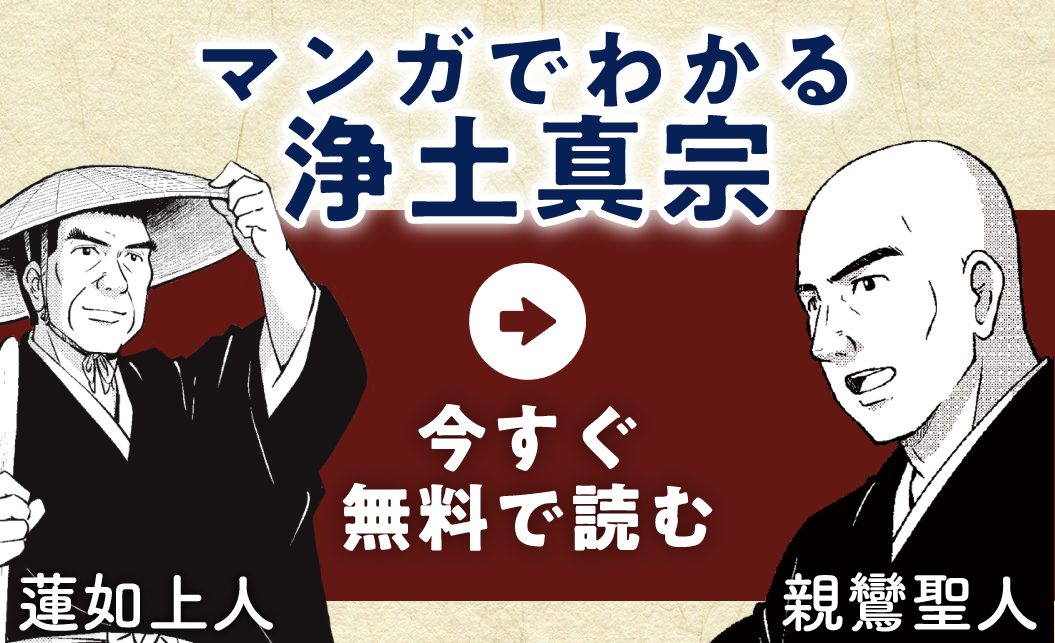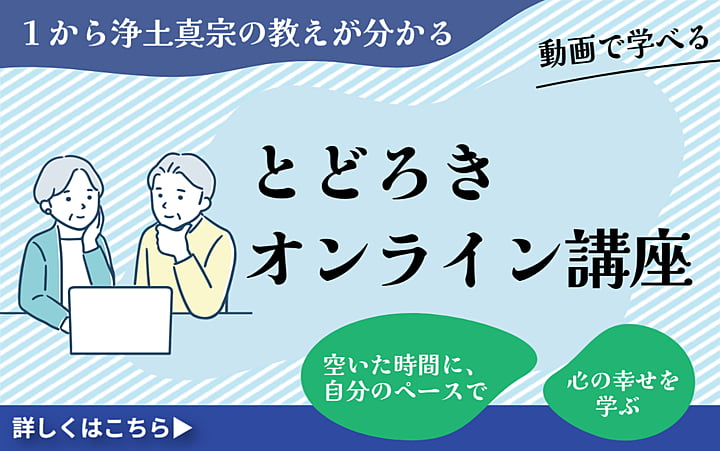木魚はなぜ木「魚」なの?|浄土真宗に木魚がない理由
テレビ朝日系のテレビ番組「グッド!モーニング」の「ことば検定プラス」で2月22日に、「お坊さんが叩く木魚はなぜ魚なのでしょうか」という問題が出ました。
答えは次のうちどれでしょうか。
- 魚は食べてはいけない
- 魚は寝ないと思われていた
- 締め切りは水曜…きょうは
答えは2の「魚は寝ないと思われていた」からです。
ちなみに3は「木(もく)ギョ!」のだじゃれです。
木魚は読経をするときに「ばい」や「しもく」と呼ばれる棒で叩いて鳴らすことで、リズムを整える以外に眠気を覚ます意味があります。
音を出すだけならば魚の形をしている必要はありませんが、なぜ魚の形をしているのでしょうか。
木魚が木「魚」なのはなぜ?
木魚が魚の形をしていたり、魚の彫刻がなされていたりする理由ですが、魚は寝るときに目を閉じませんが、それを見た昔の人が「魚は寝ないのだろう」と思ったため、「寝る間を惜しんで修行せよ」という意味をこめて、ただの中身をくり抜いた木ではなく魚の形になりました。
木魚は室町時代からありましたが、頻繁に使われるようになったのは江戸時代の隠元隆琦(いんげん りゅうき)という中国から来た僧侶が広めたのが始まりです。
最近の木魚は球体に近い形をしていますが、もともとは「木魚」の名前の通り、平べったい魚の形をしていました。
口の部分に「煩悩の珠」が付いており、木魚を叩くことで煩悩を吐き出させるという意味合いがありました。
木魚は桂蘭、本楠、本桑、白木などの中身をくり抜いて作られており、自然乾燥の工程だけで1~3年費やす必要があるため手間がかかります。
日本で生産されているのは愛知県が主で、特にお寺で使われるような高級なものは愛知県の愛西市で生産されています。
木魚は、天台宗、浄土宗、真言宗、臨済宗、曹洞宗、禅宗、日蓮宗などの多くの宗派で使われていますが、浄土真宗では木魚は使いません。なぜでしょうか。
木魚が浄土真宗で使われない理由
浄土真宗では「寝る間を惜しんで修行せよ」とは、勧められていないからです。
私たちは、欲の塊だから、ずっと寝る間を惜しんで修行できる者ではありません。
そんな欲の塊の私たちが絶対の幸福になれるのは、阿弥陀仏の本願だけであると親鸞聖人は、教えられています。
阿弥陀仏の本願は「仏法は聴聞に極まる」で、聞く一つで救われる教えです。
ですから、浄土真宗では、修行しなさい、信じなさい、祈りなさい、とは、一切、言われません。
阿弥陀仏の本願を聞きなさい、これ一つです。
これが浄土真宗の特徴なので、浄土真宗は「聞の宗教」ともいわれます。
阿弥陀仏の本願は聞く一つだから、阿弥陀仏の本願を聞いて、親鸞と同じ、絶対の幸福になってもらいたいと、
親鸞聖人は教えていかれました。
そのため浄土真宗では修行を促すための木魚は使われないのです。
阿弥陀仏の本願のことを「他力本願」とも言います。
他力本願についてはこちらの記事で紹介しています。
最新記事 by あさだ よしあき (全て見る)
- すべての人に真の元気を与える妙法「南無阿弥陀仏」の偉大な力(前) - 2026年1月12日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(後) - 2025年12月15日
- 念仏称えていても助からない?|親鸞聖人の教えの肝要とは(前) - 2025年11月30日
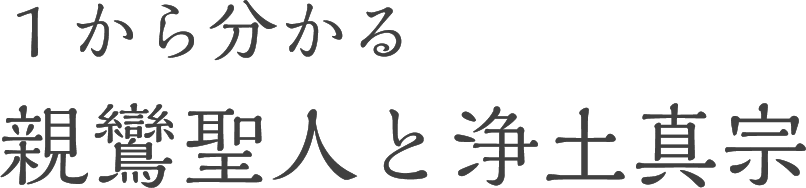

の頭も信心から|あなたは何を信じていますか?-150x150.jpg)