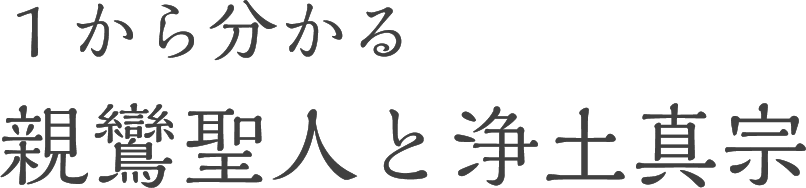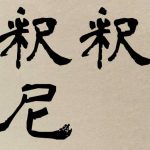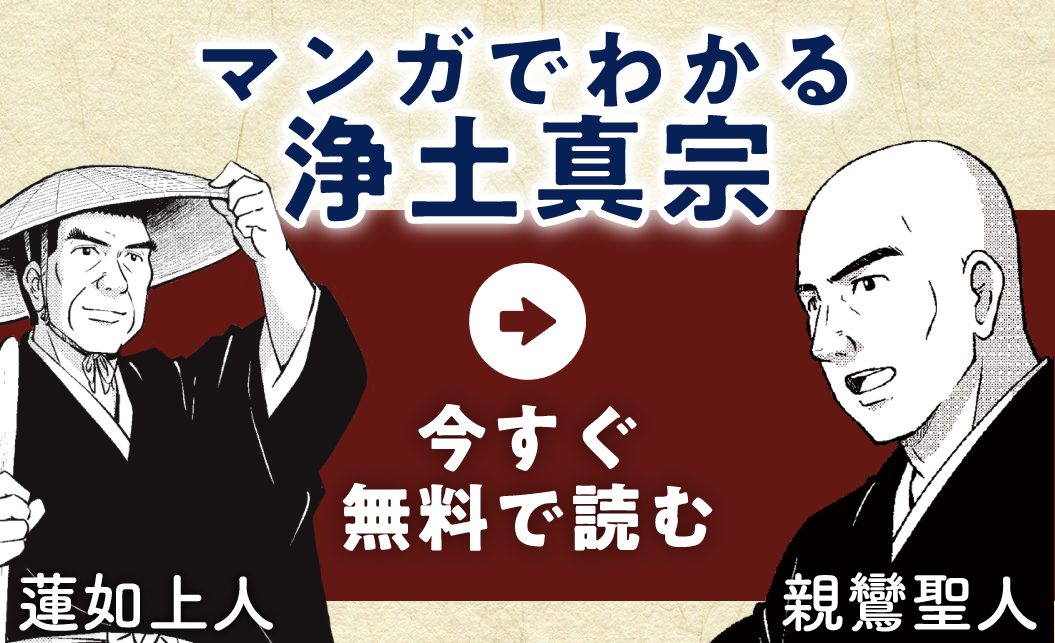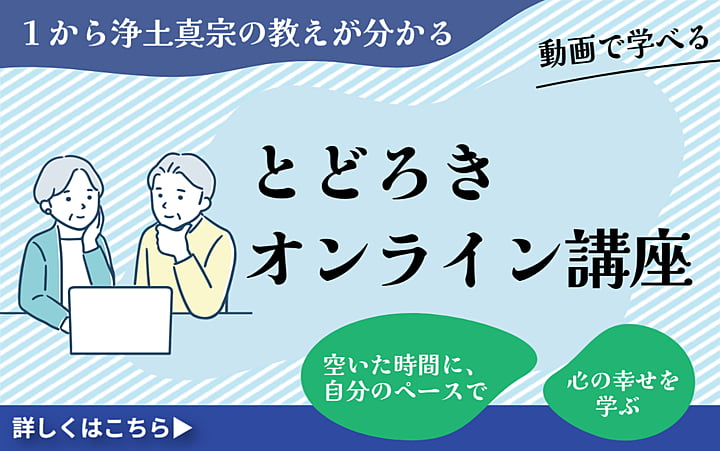浄土真宗の「彼岸」|「彼岸」の3つの謎を解く
浄土真宗のお盆|親鸞聖人の教えを聞くとお盆の過ごし方が変わります
「盆と正月が一緒に来たようだ」
よいことが続くと、こんな言葉を使うことがありますが、8月の「盆休み」は、年末年始と同様に多くの人が休みを取り、家族と過ごす大切な時間といえましょう。
では「お盆」にはどんな意味があり、私たちは何をすればよいのでしょうか。
そのお盆の過ごし方を、お釈迦さま・親鸞聖人はどう教えられているのでしょう。
さまざまな角度から教えを解説いたします。
先祖や親からどんなご恩を受けているのでしょう
8月中旬の時期を「お盆」といいますが、これはもともと仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」が由来といわれます。
暑さを残しながら、秋風が吹き始める頃、遠くに暮らす子供らが帰ってくる。
仏壇にたかれた線香に慌ただしい心も落ち着き、忘れがちだった亡き人を思い出させてくれます。
亡き人といっても親や伴侶、かわいい子供など、さまざまです。
それら故人が喜んでくれるお盆にするには、どうすればよいのでしょう。
中でも親のご恩は大きいのですが、「子を持って知る、親の恩」といわれるように、親の心は親になってみないと、なかなか分かりません。
「親は十人の子を養えども、子は一人の母を養うことなし」ともいわれます。
お釈迦さまは、私たちが親から受けた、大きなご恩を『仏説父母恩重経』というお経に詳しく説かれ、無条件で愛情を注ぎ、骨身を削り養育してくださる親の恩を、「父母の恩重きこと、天の極まり無きが如し」と教えられています。
その親にも、それぞれ両親がありました。親1人ということはありえませんから、祖父母は4人です。
祖父母にも、またそれぞれ両親があり、曽祖父母は8人……、32代遡ると、単純計算で私の先祖の数は85億8993万4590人。
実に現在の地球の人口を超える数です。
そのうちの誰一人欠けても、私は今ここに存在しませんでした。
すると、私一人のために膨大な数の先祖がいた。
それらの先祖一人一人は、両親の愛に見守られ、祝福されて、この世に生を受けたはずです。
ならば過去の多くの先祖から現在の私までずっと、深い愛情とご恩でつながっているのだ、といえるでしょう。
その深いご恩に報いるお盆にしたい……。
それが皆の願いではないでしょうか。
お経は誰のために説かれたか
生前はいるのが当たり前で、時に疎ましかった人でも、この世から去ってしまうと、生きている時に、もっと大事にできたのではないか。
あの日が最後になるなら、優しく接してあげればよかった。
恩返しできぬうちに逝ってしまった……と、悔やむ気持ちは尽きません。
そんな思いを、長いお経を読んでもらったり、立派な墓を造り手を合わせることで、静め癒やしているのかもしれません。
家族が亡くなって初めて迎える「新盆」などは、ふだん仏教に関心のない人でも、読経や墓参りをする人がほとんどです。
しかし風習として寺や墓前で読経をしてもらっても、その意味が分からねば、形式だけのむなしい儀式となってしまいます。
そもそもお経は、誰のためにあるのでしょう。
実はお経は、お釈迦さまの説法を弟子たちが書き残したものなのです。
お釈迦さまは、生きている人に本当の幸福になれる仏の教えを説かれました。
当然ながら、死者に対する釈迦の説法は一つもありません。
すべてのお経には「生きている人を幸福にする教え」が説かれているのです。
だからお盆は、チンプンカンプンの読経で「これで、死んだじいさんが喜んでくれたのかなぁ」と思って終わるのではなく、生きている私たちが、お経の中の「誰もが本当の幸せになれる教え」を聞かせてもらってこそ、意味があります。
故人のもっとも喜ぶこと
亡くなった親や先祖、伴侶や子供を本当に喜ばせるには、どうすればよいか、と真面目に考えてみると、私自身が自分の子孫、家族に何を望んでいるかを考えてみれば分かります。
生きていれば、いろんな困難や災難がやってきますが、わが子にはどんな苦難も乗り越えて、正しく生きてほしい。そして真の幸福になってほしい、これ一つではないでしょうか。
とすれば、私たちが正しく生きて、まことの幸せになることが、亡き先祖の最も喜ぶことであり、私の命を生み育んでくれたご恩に報いることになりましょう。
この世の幸福は、どんなに懸命に努力して手に入れても、しばらくすると色あせ、崩れ、なくなって悲しみに沈みます。
「何のために生きているのかナァ」
浄土真宗の「彼岸」
苦しみの岸から幸せな岸に渡る方法
仏教の伝統行事「お彼岸」には、実は私たちにとって大事なメッセージが込められています。
そのメッセージが届いた時、幸せへの扉が開かれるでしょう。
「彼岸」についての3つの謎に答えながら解説します。
なぜお彼岸は、春と秋 2回あるのか?
「ぼたもち」と「おはぎ」の違いって?
「暑さ寒さも彼岸まで」といわれるように、お彼岸には、春の彼岸と、秋の彼岸があります。
その時に食べる、あんこのお餅を、春は「ぼたもち」、秋は「おはぎ」といわれるのは、春は「牡丹」の花、秋は「萩」の花にちなんで、言い習わしているそうです。
昔の人の、季節感あふれるネーミングのセンスにちょっと感動させられますね。
仏教で「彼岸」とは「極楽浄土」のことを指します。
極楽浄土のことを、お釈迦さまが、詳しく説かれている『阿弥陀経(あみだきょう)』には、
これより西方、十万億の仏土を過ぎて世界有り、名けて極楽と曰う。
とあり、極楽浄土は、ここからはるか西の彼方にあると説かれているのです。
では、なぜお彼岸が年2回あるのでしょう。
それは極楽浄土が西にあることと関係します。
1年のうちで、春分と秋分は、太陽が真西に沈む日。
その西に沈む太陽を見ながら、極楽浄土に思いをはせるようになったのでしょう。
だからお彼岸は、春分と秋分に行われるようになったのですね。
西方にあるという「彼の岸」とはどんなところなのか?
太陽が西に沈むようにすべての人の行き着くところが「彼岸(浄土)」
では、なぜ極楽浄土は西にあると、お釈迦さまは説かれたのでしょうか。
それは、太陽も月も、最後は西の地平に沈んでいくように、すべての人が、最後、そこにたどり着かねば、落ち着かない、本当の幸せの世界が極楽浄土であるからです。
そんな、すべての人の求める本当の幸福を教えたのが仏教ですから、聖徳太子は、有名な『十七条憲法』に仏教を「四生の終帰(ししょうのしゅうき)」とも言われています。
「四生(ししょう)」とは、生きとし生けるものすべてのこと。「終帰(しゅうき)」とは、最後に帰依するところということで、最後、必ず救われる教えという意味です。
晴れた日に飛行機に乗って、山岳地帯を上空から見下ろすと、キラキラと輝く鏡の破片が散らばっているのが見えることがあります。
それは、ここかしこに点在する、名もない湖沼の群れです。
山に降った雨水は、山稜から谷を下って、水たまりを作ります。
一時、そこにとどまりますが、それは仮の宿、やがてあふれて、さらに流れ下り、次の池に流入します。
しかし、そこでも落ち着かず、しばらくするとあふれ流れて、次の湖に……そうやって、最後は、海に流れ込んで、初めて雨水は落ち着きます。
海は、あらゆる川の最後行き着く所(終帰)です。
ちょうど同じように、私たち人間が求めてやまない、究極の幸せの世界を「彼岸」といわれるのです。
「彼の岸」に対して「此の岸」がある
「彼岸」とは、「彼(か)の岸」ということで、極楽浄土のこととお話ししましたが、彼岸に対しては、「此岸(しがん)」という言葉があります。
此岸(しがん)とは、こちらの岸ということで、苦しみの人生のことです。
仏教では、「娑婆世界(しゃばせかい)」ともいわれ、耐え難きを耐え、忍び難きを忍んで生きねばならないこの世のことで、「堪忍土」ともいわれています。
娑婆について、知りたい方はこちらへ
→ 「娑婆の空気はうまい」の「娑婆」は仏教から出た言葉 仏教で娑婆の意味とは
お釈迦さまは、35歳でさとりを開かれた第一声、「人生は苦なり」と仰いました。
生きることは大変です。生きるために必死になって働き、老いや病魔とも闘わねばなりません。
人間関係のストレスに絶えずさらされ、交通事故や豪雨など、不測の事態も襲ってきます。
四方八方眺むれど、唯、愁嘆の声のみぞ聞く
善導大師(ぜんどうだいし)のお言葉です。
善導大師とは、今から1300年前、中国の浄土仏教の大成者で、親鸞聖人が最も尊敬されている一人です。
1300年前の中国も、此岸に生きる人々の姿は、現代のテレビや新聞で報道される世の中と全く変わりがなかったことの証言です。
そんな此岸から逃れて、どこかに、本当の幸せの世界(彼岸)がないかと、探し求めているのが、私たちではないでしょうか。
先ほどの例えでいうならば、私たちも、山稜に降った雨水のようなもの。
「こうしたら幸せになれる」
「これが本当の幸せじゃないか」
と、数々のチャレンジや苦労を重ねながら流れ下り、そこかしこの、幸福の水たまりに入って、一度は落ち着こうとしますが、そこに本当の安らぎはなく、やがて、次の幸福の池を求めて流れ出ます。
そうやって流れ流れて、最後、「本当の幸福」という「海」に入って初めて
「ここに求め続けてきた世界があった!」
と、心からの安らぎと満足を得ることができるようなものです。
幸せ求める人生の旅に疲れ、
,b>「どこにも本当の幸せなんかなかった」
「結局、幸せのゴールなんか人生にはないよ」
とアキラメている私たちに、
「西に向かって、ひたすら進めば、本当の幸せというゴールに到達することができますよ!」
と、究極の幸せの世界をハッキリと指し示されたのが、
「これより西方、十万億の仏土を過ぎて世界有り、名けて極楽と曰う」
というお釈迦さまの宣言なのです。
おとぎ話ではない!?本当の極楽浄土とは?
お釈迦さまが極楽浄土の様子を説かれた目的
では、私たちの求めてやまない、本当の幸せの世界といわれる極楽浄土とは、どんな世界なのでしょうか。
「極楽浄土って、仏教でよく聞くけれど、そんな世界あるわけないよ!」
「科学の進歩していない時代の、おとぎ話のようなものでしょう?」
そんなふうに思っている人もありますが、そうではありません。
親鸞聖人は、極楽浄土を「無量光明土」と仰っています。
「限りなく明るい世界」ということですが、本当は言葉を超えた絶対の世界が、極楽浄土であることを教えられているのです。
しかし、「限りなく明るい絶対の世界」と言っても分からないので、私たちに分かる感覚的な楽しみとして説かれているのが、『阿弥陀経』の教えです。
極楽浄土をお釈迦さまは、阿弥陀経に、次のように説かれています。
その国の衆生は衆(もろもろ)の苦有ることなく、但(ただ)諸の楽のみを受く、故に極楽と名く。
(意訳)
続いて、極楽には至るところに「七宝(しっぽう)の池」がある。
池には八功徳水(はっくどくすい)が満々とたたえられ、池の底には金の砂が敷き詰められている。
八功徳水とは、甘い、冷たい、やわらかい、軽い、清らか、くさくない、飲む時に喉を傷めない、飲んでおなかをこわさない、など8つの特徴のある水のことです。
池の中には、車輪のような大きな蓮華が咲き、華の色は、青・黄・赤・白、いろいろあって、それぞれが光を放って、まことに絶妙で、香りも芳醇である。
絶えず涼しい風が、そよそよと吹いて、宝石で彩られた並木や網飾りが揺れて、それらが奏でる音色は、幾千かの楽器を同時に演奏するようであると、言葉を尽くして極楽浄土の素晴らしさが表現されています。
なぜお釈迦さまは、こんな説き方をされているのでしょうか。
「猫に小判」といわれるように、人間には分かる小判の値も、猫には「ニャン」ともありがたくありません。
そんな猫に、極楽浄土の素晴らしさを伝える時には、「建物全部が魚でできているんだよ」と説けば、分かってもらえるかもしれません。
絶対の世界が、なかなか分からない私たちに、極楽浄土の素晴らしさを伝えるのに、お釈迦さまは、私たちに分かる楽しみの数々を示して説かれたのです。
お釈迦さまが、暑いインドで説かれた教えですから、道理で、清らかな水や、涼しい風など、時代や地域に合わせた比喩で、幸せな世界を説かれているのも、うなずけますよね。
これをそのままうのみにして、
「お釈迦さまはホラを吹かれたのじゃないの?」
と疑うのは、本当の極楽浄土を知らないだけなのです。
誰でも死んだら極楽浄土に往けるの?
「誰でも、死んだら、仏になって極楽へ往けるんでしょ?」
世間一般に広く思われている仏教観ですが、親鸞聖人は、
「生きている時に、仏教を聞き、阿弥陀仏に救われた(絶対の幸福になった)人だけが、死んで極楽浄土へ生まれることができるのだよ」
と教えられました。
苦しみの絶えない「此岸」を、荒波の絶えない海に例えて「難度海(なんどかい)」と仰り、そこに溺れ苦しんでいる私たちを、この世で乗せて、「彼岸」の極楽浄土まで、明るく楽しく渡してくだされる大船を、阿弥陀仏が造られたのだと、親鸞聖人は主著『教行信証(きょうぎょうしんしょう)』に仰っています。
難思の弘誓(なんしのぐぜい)は難度海(なんどかい)を度(ど)する大船
(意訳)
阿弥陀仏の本願は、苦しみ悩みの此岸から、極楽浄土の彼岸まで、明るく楽しく、必ず渡し切ってくだされる大船である。
難思の弘誓とは、阿弥陀仏の本願のことです。
阿弥陀仏の本願の大船に乗せられて、絶対の幸福になったならば、どんな波風が立とうとも、彼岸まで安楽に到達できますよ。
だから、早く、大船に乗ってもらいたいと教えられたのが、仏教なのです。
こんなお釈迦さまの教えを知れば、
「人生の旅路の行く先は何か?」
「本当の幸せってなんだろう?」
と思いを巡らせる、意義深いお彼岸になるのではないでしょうか。
まとめ
- 彼岸(彼の岸)とは、阿弥陀仏の極楽浄土のことで、親鸞聖人は、無量光明土と言われています。
- それに対して、此岸(此の岸)とは、苦しみ悩みの人生のこと。
- 苦しみ多い人生(此岸)から、無限に明るい真の幸せの世界(彼岸)に渡してくださるのが阿弥陀仏の本願という大船です。
- どんな人でも最後は、阿弥陀仏の本願に救われて、初めて、真の幸せになれるから、「四生の終帰(ししょうのしゅうき)」と聖徳太子は言われています。
- お盆に墓参りだけでいいの?今からできる恩返しの方法とは - 2018年8月30日
- 幸せの花ひらく 「因果の法則」を身につける - 2018年6月27日
- 生きる意味は何か|それをブッダはたとえ話で教えている - 2018年6月5日
では、教行信証の「難思の弘誓は難度海を度する大船」とは、どういう意味でしょうか。こちらへ。
「はー、いっそ生まれてこなければよかった」
と、タメ息をつく日々では、亡き先祖もどんなに悲しい思いをするでしょう。
仏教に説かれる幸福に生かされて初めて、「生まれてきてよかった!」の生命の歓喜があり、「こんな幸せになれたのも、生み育ててくれたおかげです。ありがとうございます」と、先祖のご恩を心から感じる身になることができるのです。
それが、亡き人のいちばん喜ぶことではないでしょうか。
仏教を聞いて、本当の幸福になってこそ、育まれた私の命は、なぜ大切なのか、なぜ地球より重いのか、人間に生まれなければ果たせない、大事な目的があるからだとハッキリ知らされるのです。
お釈迦さまが教えられたこと
お釈迦さまが、80年の生涯懸けて説かれたお経の全てを総称して、一切経(いっさいきょう)といいます。
その一切経を幾度も読み破られた親鸞聖人は、主著の教行信証(きょうぎょうしんしょう)に
それ真実の教を顕さば、すなわち『大無量寿経』これなり。
と仰り、この『大無量寿経(だいむりょうじゅきょう)』に説かれる「阿弥陀仏の本願」を聞く一つで、どんな人も最高の幸福になれると教えられました。
(大無量寿経とは、釈迦の七千余巻のお経の中で、唯一真実の経です)
“生きている今、早く真の幸福を獲得しなさい、その身になるために、人は生まれてきたのですよ”と教えられたのがお釈迦さまであり、親鸞聖人でした。
この無上の幸福に生かされた人は、仏教を伝えて下された先生のご恩、親の恩に心から感謝し、ご恩に報いようと、光に向かって努力精進せずにおれなくなります。
心静かに亡き人を思うお盆は、多くの人に愛され育まれた命が、弥陀の本願力によって自他ともに真の幸せになれる尊いご縁なのです。
では、仏教で教えられる幸福とは、どんな幸福なのか。親鸞聖人は教行信証に教えられています。